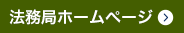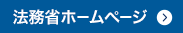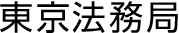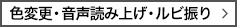Q1 書面による申請の場合における必要な書類等について教えてください。
A1 書面による供託申請の場合、供託書(供託所窓口備付けの専用のOCR用紙)の提出が必要になります。なお、供託書には押印欄はなく、供託者の印鑑は不要です。その他、以下の書面の提示又は提示が必要となる場合があります。
- 供託者が会社・法人の場合
登記所発行の代表者事項証明書等(発行から3か月以内の原本の提示が必要です。)
なお、登記されていない法人又は法人格のない社団等が供託者の場合は、代表者の資格を証する書面等の添付が必要です(供託規則第14条第2項、同条第3項)。その書面の作成年月日が3か月を超えている場合には、現在も代表者に変更はない旨の奥書が必要です。
奥書例現在も代表者に変更はない。被供託者の代表者事項証明書等は、不要です。
平成○年○月○日(奥書日)
○○(法人名)
△△(法人の資格)
□□(代表者名) 印(認印) - 委任による代理人が供託する場合
委任状(委任者の印鑑は、認印で差し支えありません。)
なお、法律事務所の補助者等が使者として来庁する場合、弁護士から補助者への委任状は必要ありません。
Q2 供託をする供託所について教えてください。
A2 裁判上の担保供託に関する管轄供託所は、各供託根拠法令に定められています(例民事保全法第4条第1項、民事訴訟法第405条等)。
例えば、東京地方裁判所又は同立川支部から仮差押命令申立事件の担保金の供託を命じられた場合は、特段の定めがない限り、東京法務局供託課、八王子支局、府中支局及び西多摩支局のいずれでも供託をすることができます。
例えば、東京地方裁判所又は同立川支部から仮差押命令申立事件の担保金の供託を命じられた場合は、特段の定めがない限り、東京法務局供託課、八王子支局、府中支局及び西多摩支局のいずれでも供託をすることができます。
Q3 手続きにはどのくらい時間がかかりますか。
A3 供託所、時期、時間帯により異なりますので、時間に余裕をもってお出でください。東京法務局供託課の場合、申請の件数及び窓口の混雑等によりますが、少なくとも30分以上を見込んでいただくようにお願いします。なお、供託書正本の交付は、供託金の納付方法(詳細は、下記Q6参照)によって異なりますので御注意ください。
現金納付・・・納付時(券種・枚数等確認後)に交付(本局、八王子支局)
日銀払込・・・日本銀行(代理店)における納付時(府中支局、西多摩支局)※1
電子納付・・・供託所での入金確認後(受領は、郵送(※2)又は来庁)
振込方式・・・供託所での入金確認後(受領は、郵送(※2)又は来庁)
※1 供託所で交付された正本を指定された日本銀行代理店に供託金及び保管金払込書とともに提出し、同代理店の領収書が押されます。
※2 切手を貼附した封筒の提出が必要です。
Q4 第三者供託の許可を得ましたが、許可書の添付は必要ですか。
A4 許可書の添付の必要はありませんが、供託書備考欄に「第三者供託である」旨を記載する必要があります。また、同欄には、併せて、本来供託すべき者の住所・本店等を、例えば「債権者の住所 東京都千代田区九段南1丁目1番15号」等のように記載する必要があります。
Q5 管轄外供託の許可(民事保全法第14条第2項)を得ましたが、許可書の添付は必要ですか。
A5 許可書の添付の必要はありませんが、供託書備考欄に「民事保全法第14条第2項の許可」と記載する必要があります。
Q6 金額が大きいのですが、納付方法はどのようにしたらいいですか。
A6 供託金の納付方法は、供託所によって異なり以下のとおりとなります。
現金納付・・・供託所の窓口で現金(又は日銀小切手)を納付いただく方法(本局及び八王子支局に限ります。)
日銀払込・・・供託受理決定後、日本銀行代理店へ現金(又は日銀小切手)で納付する方法(府中支局及び西多摩支局に限ります。)
銀行振込・・・供託受理決定後、指定の供託官口座に入金いただく方法
電子納付・・・供託受理決定後、ペイジー対応のインターネットバンキング又はATMにより入金する方法
上記供託金納付方法の詳細については、本省Webサイト(供託Q&A)を御覧ください。
Q7 供託手続き後、裁判所に供託書正本を提出したところ、記載事項の誤りを理由に不受理となりました。どのようにしたらよいですか。
A7 供託書正本の訂正はできませんので、改めて供託をする必要があるのか、それとも、供託訂正(Q8参照)で足りるのか、裁判所に確認をしてください。
改めて供託をする場合には、再供託に先立ち、当初供託した供託金の取戻請求をし、供託金を日本銀行小切手で受け取る場合には、その小切手を再供託に使用することもできます。
取戻請求には、裁判所発行の不受理証明書、供託者の印鑑証明書(発行から3か月以内の市区町村長又は登記所発行のもの)、供託者が会社・法人である場合は資格証明書(発行から3か月以内のもの)、代理人による請求の場合は委任状等が必要となります。御不明な方は、請求前に供託所に御確認ください。
改めて供託をする場合には、再供託に先立ち、当初供託した供託金の取戻請求をし、供託金を日本銀行小切手で受け取る場合には、その小切手を再供託に使用することもできます。
取戻請求には、裁判所発行の不受理証明書、供託者の印鑑証明書(発行から3か月以内の市区町村長又は登記所発行のもの)、供託者が会社・法人である場合は資格証明書(発行から3か月以内のもの)、代理人による請求の場合は委任状等が必要となります。御不明な方は、請求前に供託所に御確認ください。
Q8 供託訂正とは、どのようなものですか。
A8 供託書の記載事項の明白な誤記については、供託の同一性を害さない限り、供託訂正申請が認められます(供託準則第55条第1項)。
これは、供託書正本自体は訂正はされませんが、供託訂正申請書の副本に供託官の証明が付与され、かつ、供託所副本(電磁的記録)に訂正申請があった旨が記録されるものです。
再供託を要せず、供託訂正で足りるのかどうかは、必ず裁判所(書記官)に確認をしてください。
これは、供託書正本自体は訂正はされませんが、供託訂正申請書の副本に供託官の証明が付与され、かつ、供託所副本(電磁的記録)に訂正申請があった旨が記録されるものです。
再供託を要せず、供託訂正で足りるのかどうかは、必ず裁判所(書記官)に確認をしてください。