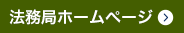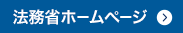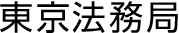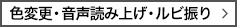不法行為(窃盗、傷害等)に基づく損害賠償債務を負う者は、被害者に債務の本旨に従った弁済行為をしたが、被害者がその受領を拒否しているなどの場合に供託をすることができます。その際、下記の事項に注意してください。
記
- 受領拒否による供託ができる例について
不法行為による損害賠償債務(民法第709条)に係る受領拒否については、例えば、以下の(1)又は(2)のような民法第494条の要件を満たしていない限り、供託を受理することはできません。- ○月○日、債務履行地において、被供託者に現実に提供したが受領を拒否された。
- 被供託者があらかじめその受領を拒否しているため、○月○日口頭の提供をしたが受領を拒否された。
- 賠償額について
損害賠償債務の一部についての弁済は、債務の本旨に従った弁済には当たらないため、その提供は、全額である必要があります。
なお、供託者は、その相当と考える損害賠償額を提供して供託することができます。ただし、これは飽くまでも供託受理の要件としてであり、実体上の適否は判断できません。
- 遅延損害金について
不法行為に基づく損害賠償債務については、不法行為日から遅延損害金が発生すると解されており(大判明43.10.22民録16-719)、元本額のみの提供は債務の本旨に従った弁済に当たらないため、供託をすることはできません。
したがって、上記1(1)又は(2)の提供時には、賠償額全額(元本)に不法行為日(初日参入)から提供日までの遅延損害金を付す必要があります。このとき、供託により消滅させる債権を特定するため、損害賠償額と遅延損害金は区分して明記してください。
参考 遅延損害金計算ソフトウェアのダウンロードについて(法務省ホームページへリンク) - 被供託者の住所について
不法行為に基づく損害賠償債務は、原則として被供託者の住所地が債務履行地になります(民法第484条)。一方で、供託は債務の履行地の供託所にしなければなりません(民法第495条第1項)。したがって、被供託者の住所が不明である場合は、供託を受理することができません。
- 取戻請求権の放棄について
取戻請求権を放棄する場合は、備考欄に「取戻請求権を放棄する」と記載してください。
- 供託書記載例
上記を踏まえて、供託所等の記載例(法務省ホームページへリンク)を参考に記載してください。