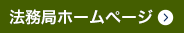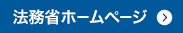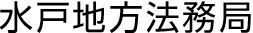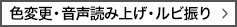相続(遺言による場合を含みます。)によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
また、遺産分割の協議がまとまったときは、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた相続登記の申請をしなければならないこととされました。
正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続登記の義務化の概要について
どうすれば相続登記ができるか
相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)
~なくそう 所有者不明土地 !~(東京法務局リンク)
- 水戸地方法務局トップページ
- 業務のご案内
- 不動産登記
- 民法・不動産登記法の一部改正と相続土地国庫帰属法について
民法・不動産登記法の一部改正と相続土地国庫帰属法について
更新日:2023年4月27日
相続登記がされないこと等により、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地や所有者が所在不明で連絡がつかない土地、いわゆる所有者不明土地が発生し、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用が阻害されることから社会問題となっています。
全国のうち所有者不明土地は九州本島の面積を超えるとされています。今後高齢化社会の進展に伴い、死亡者数の増加が予想されることからますます深刻化するおそれがあり、その解決は喫緊の課題とされています。
令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、所有者不明土地の発生の予防と利用の円滑化の観点から抜本的な見直しが図られています。
不動産登記推進イメージキャラクター「トウキツネ」が、令和3年の民法・不動産登記法改正及び相続土地国庫帰属法による新制度について動画で紹介します。
※「短編動画編」、「不動産登記法の改正編」、「相続土地国庫帰属制度編」及び「民法のルールの見直し編」は、全体版を抜粋したものです。
全体版(4分50秒)
短編動画編(19秒)
不動産登記法の改正編(2分47秒)
相続土地国庫帰属制度編(1分13秒)
民法のルールの見直し編(54秒)
1.不動産登記制度の見直し
相続登記の義務化について(令和6年4月1日から)
相続人申告登記について(令和6年4月1日から)
不動産の所有者が亡くなった場合、遺産分割の協議がまとまるまでは、全ての相続人が民法上の相続分の割合で共有している状態となります。遺産分割の協議がまとまったときは、その内容によります。
いずれの場合であっても、相続登記を申請しようとする場合、民法上の相続人や相続分を確定しなければならないため、全ての相続人を把握するための戸籍謄本等の収集が必要となります。
このため、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるよう、相続人申告登記という新たな制度が設けられました。
相続人申告登記は(1)登記簿上の所有者について相続が開始し、(2)自らがその相続人であることを申し出る制度です。この申出がされると、相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分までは登記されません。
※ 権利の取得を公示するものではないため、これまでの相続登記とは性質が異なりま
す。
住所等変更登記の義務化について(令和8年4月までに開始)
登記簿上の所有者は、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記を申請しなければならないこととされました。
正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。
公的機関との情報連携による住所等変更登記について(令和8年4月までに開始)
住所等の変更登記の手続の簡素化・合理化を図る観点から、法務局が他の公的機関から取得した情報に基づき、職権で住所等の変更登記を行う制度が設けられました。
所有者が自然人(個人)の場合、住基ネットへの照会に必要な生年月日等の情報を提供していただく必要があります。また、変更登記がされるのは、本人の了解が得られた場合に限ります。
所有者が法人の場合、商業・法人登記上で住所等に変更があれば、不動産登記とのシステム連携が行われます。
2.相続土地国庫帰属制度の創設(令和5年4月27日から)
土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したいと考えている方が増加しています。また、相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いています。
所有者不明土地の発生を抑えるため、相続や遺贈により土地の所有権を取得した方が、法務大臣の承認により土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されました。
相続土地国庫帰属制度の概要について
申請者について
申請ができるのは、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限られます。)により土地の所有権を取得した相続人となります。
土地が共有地である場合には、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請する必要があります。
この場合、他の共有者については、相続等以外の原因により持分を取得した場合であっても申請することができます。
帰属ができない土地について
土地の管理コストが国へ不当に転嫁されることやモラルハザードの発生を防止するため、国庫帰属の要件が法令で具体的に定められています。以下のいずれかの要件に該当する土地については国庫帰属ができません。
(1)申請ができない土地
・建物の存する土地
・担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
・通路その他の他人による使用が予定される土地として、以下の(1)から(4)が含まれ
る土地
(1)現に通路の用に供されている土地
(2)墓地内の土地
(3)境内地
(4)現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地
・土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地
・境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある
土地
(2)承認ができない土地
※(1)と異なり、審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地を指
します。
・崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を有するもの
※崖は勾配30度以上であり、かつ高さが5メートル以上のものが該当します。
・土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上
に存する土地
・除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存
する土地
・隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をす
ることができない土地
(例)
他の土地に囲まれて公道に通じない土地であるにも関わらず、現に民法上の通行権
利が妨げられている土地
・そのほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用や労力を要する以下の土
地
(例)
土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせ
る土地
申請方法について
申請書を提出する場合は、以下のいずれかの方法によります。
(1)水戸地方法務局不動産登記部門(029-221-5130)に連絡の上、申請者
本人又は法定代理人(未成年後見人・成年後見人等)が来庁する方法
※使者による提出が可能です。
(2)水戸地方法務局不動産登記部門に書留郵便(封筒と切手をご自身で用意)又はレタ
ーパックプラスにより、申請書と添付書類等を送付する方法
※国庫帰属の申請書が入っていることを明記してください。
【送付先】
〒310-0061
水戸市北見町1-1 水戸法務総合庁舎
水戸地方法務局不動産登記部門宛て
※相続土地国庫帰属制度の標準処理期間は8か月です。
申請書は以下の様式を使用して作成することが可能です。作成に当たっては、記載例
をご覧ください。
申請書様式(単独申請の場合)
申請書記載例(単独申請の場合)
申請書様式(共同申請の場合)
申請書記載例(共同申請の場合)
また、申請書に添付していただく書類は以下のとおりです。
〇全ての申請者について必須の書面
(1)申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
(2)申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
(3)申請に係る土地の形状を明らかにする写真
(4)申請者の印鑑証明書
添付書類(1)様式
添付書類(2)様式
添付書類(3)様式
添付書類(1)~(3)記載例
○遺贈によって土地を取得した相続人について必須の書面
(5)相続人が遺贈を受けたことを証する書面
〈具体例〉
・遺言書
・亡くなった方の最後の戸籍全部事項証明書、除籍謄本又は改製原戸籍謄本
・亡くなった方の除かれた住民票又は戸籍の附票
・相続人の戸籍一部事項証明書
・相続人の住民票又は戸籍の附票
〇申請者と登記名義人が異なる場合について必須の書面
(6)土地の所有権登記名義人又は表題部所有者から相続又は一般承継があっ
たことを証する書面
〈具体例〉
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書、除籍謄本又は改
製原戸籍謄本
・亡くなった方の除かれた住民票又は戸籍の附票
・相続人の戸籍一部事項証明書
・相続人の住民票又は戸籍の附票
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
〇任意で添付する書面
・固定資産税評価証明書
・申請土地の境界等に関する資料
※申請書と添付書類の作成、よくある質問等について、詳しくは法務省ホーム
ページをご覧ください。
手続にかかる費用について
(1)審査手数料
土地一筆当たり14,000円となります。
なお、手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果却下
・不承認となった場合でも、手数料を返還できませんのでご注意くだ
さい。
(2)負担金
土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につ
き、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額
を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません。
※法務省ホームページに、負担金の自動計算シートを掲載しています。
相談について
水戸地方法務局不動産登記部門において、対面(又は電話)での相談を実施しています。
原則として、茨城県内の土地を国庫に帰属させる場合について、相談に対応します。
このほか、対象の土地が遠方にある場合、茨城県内にお住まいの方の相談に対応します。ただし、個別事案の具体的な内容までお答えできない場合があります。
相談は事前予約制です。予約がない場合、相談に対応できません。予約は法務局手続案内予約サービスから行っていただくようお願いいたします。
※インターネット環境がない場合、水戸地方法務局不動産登記部門(029-221-5130)にお問合せください。
3.遺産分割の見直し(令和5年4月1日から)
相続が発生してから遺産分割の協議がされないまま長期間放置されると、更に相続が発生して多数の相続人が共有している状態となる結果、遺産の管理・処分が困難になります。
また、遺産分割をする際は、相続分の算定に当たり、生前贈与や療養看護等の特別の寄与をしたことを考慮することが一般的とされていますが、長期間放置されるとこれらの書証が散逸してしまい、相続分の算定が困難になるといった問題があります。
これまで、遺産分割を行うに当たり期間の制限はありませんでしたが、生前贈与等を考慮した相続分の割合による遺産分割に限って期間の制限を設けることで、遺産の共有している状態の早期解消を促すこととされました。
相続の開始から10年を経過した後にする遺産分割は、生前贈与等を考慮した具体的相続分ではなく、民法上の相続分又は遺言により被相続人が指定した相続分によるものとされました。
※詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。