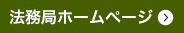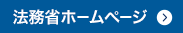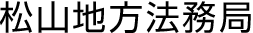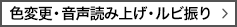A. 全国の登記所間において、土地・建物に関する登記事項証明書の交付請求を、相互にすることができる「登記情報交換サービス」があります。
登記事項証明書の交付を請求するときは、このサービスを利用して、最寄りの登記所で、その登記所の管轄外の登記事項証明書を請求し、受け取ることができます。
このサービスを利用するときは、登記事項証明書を請求しようとする土地・建物の所在(○市○町○丁目○番地)と地番・家屋番号をあらかじめ調べておいてください。
なお、土地・建物の地番・家屋番号は、いわゆる住居表示と一致しないことが多いので、正しい地番・家屋番号を、登記完了証や登記識別情報通知書又は登記済証(いわゆる権利証)等で確認してください。
- 松山地方法務局トップページ
- よくある質問
- 不動産登記に関するよくある質問
不動産登記に関するよくある質問
更新日:2024年6月3日
Q.遠く離れた土地・建物の登記事項証明書(謄抄本)を請求することができますか。
Q.住居表示番号しか分かりませんが、土地の登記事項証明書(謄抄本)は請求できますか。
住居表示番号と地番は別のものなので、住居表示番号では、土地・建物の特定ができず、登記事項証明書(謄抄本)や登記事項要約書の交付や閲覧をすることができません。
法務局窓口の地番対照表や住宅地図、または所有者の方が保管している権利書等を確認の上、請求してください。
Q.権利証(登記済証)を無くしてしまいました。再発行はしてもらえますか。
A. 権利証は所有権等の登記が終わったときに法務局から申請人に交付されるものですから、権利証の再発行はできません。
権利証を紛失したからといって、権利が無くなったり、その登記が抹消されるわけではなく、権利関係そのものには、直接影響はありません。
1 権利証とは
権利証とは、法令上は「登記済証」という名称であり、登記が完了した際に登記所から買主等の登記名義人に交付する書面です。この登記済証は、例えば登記記録上の登記名義人が登記義務者(売主)として所有権の移転の登記を申請する場合に、登記名義人本人からの申請であることを確認する資料として登記所に提出することとされていることから、一般的には「権利証」とも呼ばれています(平成16年の不動産登記法の改正により、現在は、登記済証(権利証)に代わる本人確認情報手段として、登記識別情報の制度が導入されています。)。
2 権利証の不正使用について
紛失した権利証を誰かが悪用し、勝手に所有権の移転の登記や抵当権の設定の登記をしてしまうのではないかということが考えられますが、このような登記の申請には、登記済証(権利証)のほかに、印鑑証明書等の添付情報が必要となりますので、実印や印鑑証明書の管理をしっかり行っていれば、勝手に登記されるということはありません。また、登記済証(権利証)を紛失しただけでは、登記記録上の権利には何らの影響もありません。
登記名義人ではない者が、他人の登記済証(権利証)を用いて不正な登記を行うことは、一般的には容易なことではなく、仮に、登記名義人でない者が他人になりすまして不正な登記をしたとしても、その登記は無効であり、その行為は犯罪となります。
3 不正登記防止申出の制度について
登記済証(権利証)を取得した者が、登記名義人になりすまして不正な登記を行う可能性がまったくないとは言い切れませんし、不正な登記がされた場合には、登記名義人が思わぬ損害を被るおそれも否定できません。このような場合に、登記名義人の権利を防衛するため、不正登記防止申出の制度があります。
不正登記防止申出の制度は、不正な登記がされる差し迫った危険がある場合に、申出から3か月以内に不正な登記がされることを防止するための制度であり、権利の移動を禁止する趣旨の制度ではありません。
紛失した権利証を不正な登記(犯罪)に利用される差し迫った危険があるというような、具体的な不安がある場合には、3か月ごとに不正登記防止申出の手続をしていただくことになります。
なお、不正登記防止申出の手続は、申出人本人の出頭を原則としていますが、本人が登記所に出頭できない止むを得ない事情があると認められる場合には、委任による代理人が登記所に出頭してすることもできますので、申出先の登記所に御相談ください。
4 登記制度における代替措置
登記済証(権利証)は、当該不動産に関する所有権の移転の登記などに使用することになりますが、登記済証(権利証)を提供することができない正当な理由があるときは、登記済証(権利証)を提供することなく他の方法により申請ができることとされています。具体的には、登記済証(権利証)による本人確認に代えて、登記所から登記名義人あてに、「事前通知」(不動産登記法第23条第1項)により本人であることの確認をさせていただきます。
この「事前通知」とは、登記済証(権利証)を提供すべき登記名義人の住所地にあてて、本人限定受取郵便により、登記の申請があった旨、及びその申請の内容が真実であるときは2週間以内にその旨の申出をすべき旨の通知をし、この通知に対して、2週間以内に申請に間違いがない旨の申出がされることをもって、本人からの申請であることを確認するというものです。
また、登記の申請を司法書士等の資格者に委任して行う場合には、「事前通知」の方法によらずに司法書士等の資格者が本人であることを確認した旨の書類(「本人確認情報」)を提供していただく方法や公証人に同様の書類を作成してもらい、提供していただく方法もあります(不動産登記法第23条第4項)(なお、事前通知の方法では手数料はかかりませんが、司法書士等に「本人確認情報」を作成してもらう場合には、そのための手数料がかかる場合もありますので、利用される場合は、あらかじめ御確認ください。)。
Q.他人の土地の登記事項証明書(謄抄本)を請求することはできますか。
A. 土地・建物・会社等の登記事項証明書(謄抄本)は、どなたでも請求することができます。
なお、請求事項(地番、会社名等)を特定する必要があります。
Q.地番が分からないと登記事項証明書(謄抄本)は発行できないのですか。
A. 不動産の登記事項証明書(謄抄本)は請求された地番に基づき発行していますので、地番が分からないと発行できません。恐れ入りますが権利証(登記済証)等で地番の確認をお願いいたします。
地番が不明な場合は、周辺の地番が分かれば、地図(公図や住宅地図など)を頼りに地番を探せる場合もあります。
Q.登記簿謄本と登記事項証明書の違いは?
A.
1 登記所は、磁気ディスクに登記記録を登録し、コンピュータ・システムにより登記事務を行っていますが、このコンピュータシステムを利用して登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明したものが、登記事項証明書です。
一方、コンピュータシステムで取り扱うことができない登記記録については、 従前と同様に「紙」の登記簿を使用していますが、登記簿の全部を複写して証明したものが登記簿謄本であり、一部を複写して証明したものが登記簿抄本です。
これらの登記事項証明書と登記簿謄抄本は、作成の方法は重なりますが、登記されている事項を公示するという同じ効力を持つものです。
2 登記記録は、1筆(1区画)の土地又は1個の建物ごとに表題部と権利部に区分して作成されています。
さらに、権利部は甲区と乙区に区分され、甲区には所有権に関する登記事項が、乙区には所有権以外の権利に関する登記事項がそれぞれ記録されています。
(1)
表題部の記録事項 土地・・・所在、地番、地目(土地の現況)、地積(土地の面積)など
建物・・・所在、家屋番号、種類、構造、床面積など
(表題部にする登記を「表示に関する登記」といいます。)
マンションなどの区分建物については、その建物の敷地に関する権利(敷地権)が記録される場合があります。この敷地権についての権利関係は、区分建物の甲区、乙区の登記によって公示されます。
(2)
権利部(甲区)の記録事項 所有者に関する事項が記録されています。所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したかが分かります(所有権の移転の登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など)。
(3)
権利部(乙区)の記録事項 抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録されています(抵当権設定、地上権設定、地役権設定の登記など)。